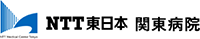大江院長によるインタビュー 2
治療はほぼお腹の中で完結
合併症のリスクを軽減
大江:なるほど。ロボット支援下手術は他の術式と比べて少し医療費は高くなってしまいますが、合併症や成果の上で有益な部分も多いということですね。ほぼお腹の中で治療が完結できるのもメリットではないでしょうか?
田中:そうですね。検体を取り出すこと以外はほぼお腹の中で処置ができ、ほとんど完全腹腔鏡下といえます。癒着が起こりにくいのがメリットです。
中村:膀胱全摘をした後、新膀胱やストーマを造設しますが、お腹の中でほぼすべての工程を行います。術中に腸管が乾かないので、腸閉塞のリスクを下げることができます。
大江:私の専門である手の外科でもそうですが、体の外で処置していると組織が乾いて障害が起こることがあります。組織障害を起こさないためには重要なポイントですね。あと、人の手では届かないようなところに届いたり、しっかり固定されて手ブレもない。
田中:左右2本ずつで4本あるアームのうち、真ん中の2本のどちらかをカメラにしますが、外側の右手で持ち上げたら足でシフトチェンジし、固定した状態で別のアームを動かすので、止まった状態で次の処置ができるんです。
大江:もう1本の手が助手になるようなイメージですね。
中村:ロボットに専用のアームをつければ自動吻合もできるので、切りながらステープラーでカチカチと留めていけるんです。
田中:ただし、糖尿病やステロイド服用の人など血管リスクの高い人は血流が悪くなって傷口が開いてしまうことがあるので、注意が必要です。
精密な動きで負担を少なく
術後の機能温存にも期待
大江:合併症が少ないことのほかに、患者さんにはどんなメリットがありますか?
田中:痛みは少ないですよね。精密な動きができるので、患者さんの組織が受けるダメージも限りなく小さいです。術後の採血で炎症の値が大きく上がらない人もいて、それには最初、驚きました。
中村:前立腺の全摘手術では、術後の尿失禁がいちばんの問題になってくるのですが、ロボットの拡大視野できれいに筋肉や神経が見える状態で手術をすることで、周囲の臓器を温存して悪い部分だけを取ることができ、術後のおしっこの漏れをかなり減らすことができるほか、必要な人には勃起の神経を残してあげることも。そこが大きなメリットですね。
大江:では最後に、地域の方にお伝えしたいことはありますか?
中村:泌尿器科では、志賀淑之部長をはじめロボット支援下手術の豊富な経験のある術者がそろい、2021年1~12月で前立腺の手術だけで153件という症例数となっています。また、術後の早期回復プログラムに多職種で取り組むことで、合併症が少なく早期に回復できるようにトータルで取り組んでいます。
田中:ロボットというアプローチで患者さんの体に本当に優しい手術を提供しています。順調な胃がんのケースであれば入院期間も約1週間となっていますので、選択肢の1つに入れてください。
先生にお話を聞きました!
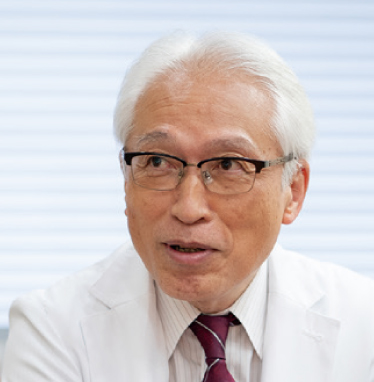
院長 大江 隆史
1985年東京大学医学部卒業。専門は整形外科全般、手外科。名戸ヶ谷病院病院長を経て、
2015年4月当院整形外科主任医長、2018年4月整形外科部長、2020年4月副院長兼務、2021年4月病院長就任。日本整形外科学会整形外科専門医、日本手外科学会手外科専門医。

泌尿器科 主任医長 中村 真樹
2001年東京大学医学部卒業。2011年東京大学大学院医学系研究科外科学専攻修了。専門は、泌尿器悪性腫瘍、ロボット支援下手術。東京大学医学部附属病院などでの勤務を経て、2021年より現職。東京大学医学部非常勤講師。日本泌尿器科学会泌尿器科専門医。
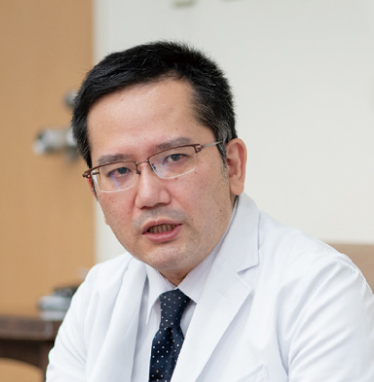
外科 医長 田中 求
2005年慶應義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学病院などでの勤務を経て2022年より現職。専門は、ロボット支援下手術、食道がん・胃がんに対する低侵襲手術。日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消化器外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医。