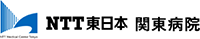Contents
進行肺がんの治療は個別化の時代 多職種のチームで患者さんに並走
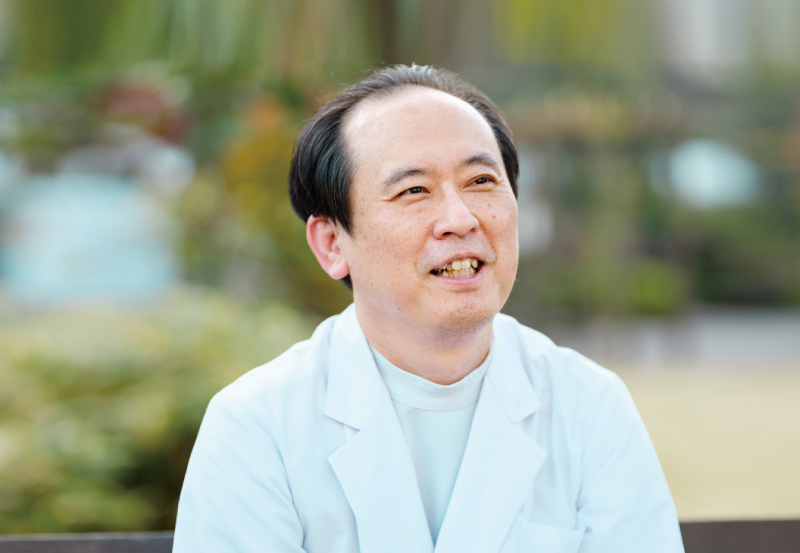
患者さんの心身の痛みを多職種のチームでケア
近年、手術が困難な進行肺がんの治療効果は分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬の登場により大きく変わりました。がん遺伝子による肺がんに対し、特定の遺伝子の働きをピンポイントで阻害する分子標的薬を適切に用いた場合、生存値の大幅な延伸が期待できるようになりました。また、ノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑先生らの研究成果による免疫チェックポイント阻害薬についても、低下した免疫機能を整えてがん細胞と戦う力をサポートする特性によって治療成績のさらなる向上が見込まれています。かつては打つ手がなかった症例も、新薬の台頭により一筋の光明が見えるようになりました。しかし、こうした個別化治療は、開始までに2~3週間かかるのが一般的です。その間の患者さんとご家族の心労を少しでも軽減するべく、当院では早期に緩和ケアチームが介入して心身の痛みをケアします。
肺炎などの合併症を防ぐには喫煙習慣から卒業する「卒煙」が鍵
肺がんは、初期にはあまり自覚症状がありません。しかし、3カ月治療が遅れると10年生存率が10%下がるともいわれていることから、早期発見のために、定期的な検診を欠かさないようにしましょう。また、肺がんの患者さんのお話を聞くと、非常に多くの方に喫煙習慣があります。肺がんと喫煙に因果関係があることは明白で、予防や治療にはタバコと縁を切る必要があります。「治療が必要な状態になってからやめても意味がないのでは」と仰る方もいますが、術後に肺炎などの合併症を起こしやすくなることも考えて、喫煙習慣から卒業する「卒煙」をお勧めしています。
ロボット支援下手術の登場で手術は確実性を増している

患者さんのステージとプロファイルをもとに手術の適応を見極める
呼吸器外科では、肺がんの疑いでご紹介いただいた患者さんや、CT検査ですりガラス陰影と呼ばれる淡い影が見つかった患者さんに対して、まずは手術が可能か否か、手術を行う場合はどの術式、アプローチ法が最善かを検討します。判断材料となるのは、進行度を表すステージ(病期)、および年齢、体力、併存症の有無、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の有無といった患者さん一人ひとりのプロファイルです。具体的には、早期の肺がんや、リンパ節転移のない肺がん、リンパ節転移があっても限局的な肺がんで、全身状態が良ければ手術適応となります。手術が決まったら、がんを含む肺葉と、転移する可能性があるリンパ節を取り除く「肺葉切除」と「リンパ節郭清」が標準治療ですが進行度や腫瘍のある場所により、個別にカスタマイズした手術計画を立案します。
死角が減り難易度が下がるロボット支援下手術
外科手術のアプローチには、気管支血管再建が必要な進行例、再手術例などで選択される「開胸手術」、胸腔鏡を使う「胸腔鏡下手術」、ロボットを使用する「ロボット支援下胸腔鏡下手術」があります。当院では、侵襲が少なく、かつ開胸手術と同等の処置が可能な胸腔鏡下手術を主な手法とし、ロボット支援下胸腔鏡下手術も積極的に行っています。ロボット支援下胸腔鏡下手術は、特殊なカメラで術野を立体視しながら、人の手よりも柔軟に動くロボットでより精密な鏡視下手術を行うものです。ロボットを使うことで死角が減り、手術の難易度が下がって確実性が上がると考えています。ロボット技術は日進月歩で進化しています。今後は、手術の手技と同様に、ロボットを扱う技術の高さや経験が医師に求められるようになるでしょう。
診療科の枠を超えワンチームで治療にあたる
手術が困難な進行性肺がんと診断された場合や、リンパ節に転移があり、術前に抗がん剤を投与する必要がある場合は、呼吸器内科が化学療法や放射線治療を行います。化学療法を行って、進行度が下がれば外科手術も可能となります。術後も再発予防のための化学療法を行うなど、肺がん治療において呼吸器内科と呼吸器外科の連携は欠かせません。診療科の枠を超えたワンチームとして、患者さんにとって最適な治療と、より良い治療成績を追求しています。

先生にお話を聞きました!

呼吸器内科 部長 臼井 一裕
1993年東京大学医学部卒業。東北大学加齢医学研究所を経て現職。専門分野は呼吸器内科一般、肺がん。日本呼吸器学会呼吸器専門医、日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医、日本内科学会総合内科専門医。

呼吸器外科 部長 松本 順
1989年山梨大学医学部卒業後、東京大学胸部外科入局。日本赤十字社医療センター、総合病院国保旭中央病院などを経て、2011年よりNTT東日本関東病院呼吸器外科。胸腔鏡、ロボット支援下手術が得意。