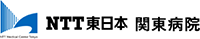さまざまな疾患の予防・改善に効果があり、万能薬ともいわれる「運動」。しかし、どんな運動がなぜ有用なのかを示す明確な根拠はありません。当院では、運動が体に及ぼす影響から運動の万能性を証明することにつながる臨床試験を実施し、運動が苦手な人・運動できない人でもできる、運動に代わる効果的な生活習慣の確立をめざします。
運動で疾患が改善する理由と効果的な運動を探るための臨床試験
臨床試験は医療の進化に不可欠
NTT東日本関東病院では、治験センターを開設し、適切かつ安全な臨床試験の実施を推進しています。基礎研究や動物による非臨床試験で一定の結果が得られた診断方法、治療方法などについて、患者さんの協力を得て安全性と有効性を調べています。新たに開発された薬や手法がどれだけ有用でも、臨床試験を経て厚生労働省の承認を得なければ一般に使用することはできません。治療法の確立や進化において、臨床試験は不可欠なのです。当院で実施している臨床試験については、ホームページ上で随時公開・募集しているほか、臨床試験の条件に該当する患者さんに対して担当の医師が参加を推奨することもあります。
メカニカルストレスの臨床試験を開始
今回、当院で実施する臨床試験の1つに、「メカニカルストレスの試験」が加わることになりました。これは、「細胞のメカニカルストレス受容」をテーマに基礎研究を続ける澤田泰宏先生が、当院糖尿病・内分泌内科の林道夫部長の協力を得て行うものです。
メカニカルストレスとは、日常生活や運動を通じて細胞や組織に加わる物理的な刺激のことです。澤田先生は、それまで骨の強化・形成に焦点を当てていたメカニカルストレスについて、脳や内臓の恒常性維持や抗炎症・抗老化作用があることを発見し、マウスを用いた非臨床研究を進めてきました。わかりやすく言うと、「適度な運動が体に良いのはなぜか」を科学的に明らかにするための研究です。
今回、澤田先生の研究に以前から注目していた当院の大江隆史院長の進言により、澤田先生とは東京大学医学部時代の同級生であり、臨床試験の対象となり得る患者さんを多く診ている林部長に白羽の矢が立ちました。
臨床試験内容
臨床試験用に開発された、1秒間に2回上下振動する椅子に30分座っていただきます。糖尿病の診断の指標であるHbA1cに変化が現れる期間を加味し、臨床試験期間は週3回・3ヵ月としています。
こんな椅子に座ります!

座っていただく椅子は座り心地にこだわって開発されました。また、細胞に良い効果を効率よく起こすと考えられている刺激も緩やかで、臨床試験中はリラックスしてお過ごしいただけます。実際、高血圧の患者さんに対して臨床試験を実施した際には、寝てしまわれる方もいました。
糖尿病と脂肪肝を対象にスタート
例えば、糖尿病や脂肪肝と診断された場合、医師は「適度な運動」を勧めます。実際、運動によって血圧や血糖値が低下することは事実で、運動が疾患の改善に有用であることは明らかです。しかし、適度な運動がどのように疾患に作用するのか、その機序はわかっていません。また、具体的にどんな運動をすると効果があるのかについても、明確な答えはありませんでした。今回の臨床試験は、糖尿病、または脂肪肝の診断を受けた患者さんを対象としてスタートし、非臨床研究で効果が見られた運動の効果を確認します。結果次第では、うつ病や認知症といった疾患にも臨床試験の対象を拡大していく予定です。
「当該の運動は、椅子に座ったまま心地良い振動に身を委ねるものであり、運動の苦手な方、諸事情で運動に取り組めない方に対する運動療法の提供にもつながることを期待しています」(林部長)「臨床的に意味がある研究であることを証明するには、多くの患者さんのご協力が必要です。臨床試験対象に該当する方は、ぜひご参加ください」(澤田先生)
お問合せ
糖尿病・内分泌内科
03-3448-6111(代表電話)
※臨床試験参加は当院糖尿病・内分泌内科への受診及び医師の判断が必要です。詳しくはお問い合わせください。
先生にお話しを聞きました!

糖尿病・内分泌内科部長 林 道夫
1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院、がん研究会がん研究所、米国ハーバード大学を経て現職。日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医指導医、日本糖尿病学会糖尿病専門医指導医。「運動嫌いの方にも運動習慣をつけていただけるのではないかと、今回の臨床試験に大いに期待しています」

国立障害者リハビリテーションセンター病院 臨床研究開発部長 澤田 泰宏
1985年東京大学医学部卒業。整形外科医として約15年勤務後、コロンビア大学留学。以来、細胞のメカニカルストレス受容をテーマに基礎研究を行う。シンガポール国立大学生物学部准教授、同メカノバイオロジー研究所准教授を経て2014年より現職。