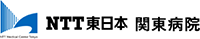血液内科では、白血球、赤血球、血小板などの血液細胞に異常が生じる疾患の治療を行っています。これらの疾患は大きく分けて良性疾患と悪性疾患の2種類に分類されます。
良性疾患
再生不良性貧血や発作性夜間ヘモグロビン尿症などの「造血不全症」や、自己免疫性溶血性貧血や免疫性血小板減少症を代表とする「自己免疫応答の異常による血球減少症」があります。これらの疾患は、抗胸腺免疫グロブリンや免疫抑制剤、補体阻害薬、抗体薬などで治療されます。
悪性疾患
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群などの「造血器悪性腫瘍」と、真性多血症、本態性血小板血症、骨髄線維症などの「骨髄増殖性腫瘍」が含まれます。これらの悪性疾患の治療には、抗腫瘍薬(抗がん剤や分子標的薬、抗体薬)を中心とした薬物療法が主に用いられます。また、ドナーから提供された造血幹細胞を移植することで正常な造血能を回復させる幹細胞移植も行われます。最近では、分子標的薬や抗体薬などの新規薬剤が次々と開発されており、CAR-T細胞療法や二重特異抗体薬なども臨床応用されています。白血病やリンパ腫の腫瘍細胞のゲノム解析を行い、最適な薬剤や治療法を選択することも重要です。当院はがん診療連携拠点病院として、東京大学などと連携しゲノム医療を提供しています。
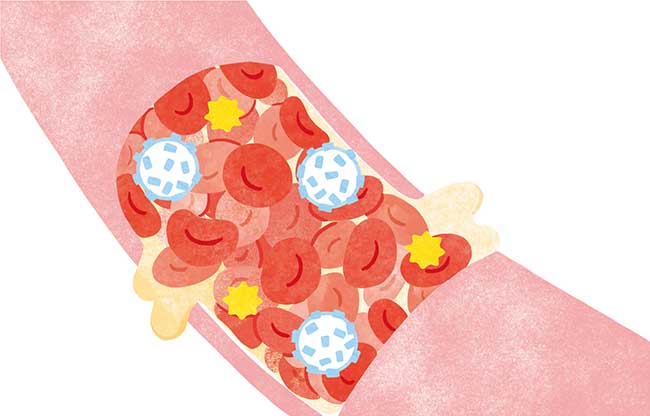
「AYA世代」の患者さんへの取り組みと課題
再生不良性貧血の好発年齢は10-20代と60-70代にあり、慢性の自己免疫性血小板減少症では20-40代と60-80代に好発年齢があります。また、小児期から20代においては白血病と悪性リンパ腫は主要な悪性疾患です。したがって血液内科では若い世代の患者さんを診療することが他科に比べて多くなっています。当血液内科では毎年5~10人程、16歳から39歳の「AYA世代」の患者さんを新規に診療しています。
AYA世代は、身体的・精神的に発達・成熟途上にあり、社会的な移行期にあたります。学業、仕事、恋愛、結婚、出産、子育てなど、ライフステージの変化が集中しているため、同じ疾患で同じ治療に取り組む場合でも個々に状況が異なります。治療は数か月から数年に及び、長期の入院が必要な場合もあるので、進級、進学、就職に影響を与えるほか、経済的な問題も大きくなります。治療による体力低下や容姿の変化、抗がん剤による生殖能力への影響も考慮する必要があります。また、AYA世代の患者さんは同世代の入院患者さんが非常に少ないため、辛さや孤独感を抱えやすい傾向があります。
当科では、定期的に問診票やアンケートを行って、患者さんのお悩みやニーズを早期に的確に把握することに努め、医師、看護師、薬剤師、臨床心理師、リハビリテーション担当者、栄養士などの多職種が連携して関わり、さまざまな視点からの支援を行うようにしています。本人からの依頼と同意のもとで学校や職場への情報提供や説明を行うこともあります。コロナ禍の間にIT化が進んだことによって、入院中もオンライン授業や在宅ワークで学業や仕事を継続できる環境が整いつつあります。また、抗がん剤による妊孕性の低下に対する支援として、精子や卵子の凍結保存を希望する患者さんには専門クリニックを紹介しています。白血病や高悪性度リンパ腫の治療には迅速な対応が必要なので、患者さんの希望に沿えない場合もありますが、正確な情報提供を行い、不安の軽減に努め、治療が円滑に進むようにチームワークを図りながら診療を行っています。
このように、血液内科ではAYA世代の患者さんに対して、個々の状況に応じたきめ細やかな支援を提供し、治療と生活の両立をサポートしています。
関連ページ
- ■ 小児・AYA世代のがんの罹患率:https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/child_aya.html
- ■ 再生不良性貧血について:https://www.nanbyou.or.jp/entry/106
- ■ 免疫性血小板減少症:https://www.nanbyou.or.jp/entry/157
不安なことなんでもご相談ください!「がん相談支援センター」
相談方法
電話相談または対面相談(費用無料) (対面相談時はプライバシー確保のために個室相談室もございます)
受付時間
曜日:平日
時間:9:00 ~ 17:00
休日:土・日、祝日・振替休日
年末年始(12/29-1/3)
対面相談受付
当院1F中央玄関を入り、右側の総合案内の電話受付へお越しいただき、受付の電話で②番を選択し、呼び出してください。

ご相談・対面相談ご予約 お問い合わせ先
先生にお話を聞きました!
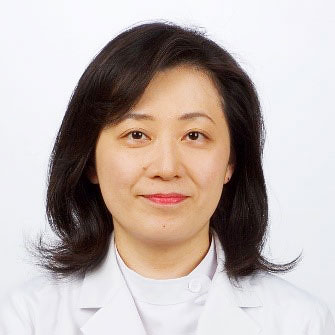
血液内科 医長 木田 理子
1994東京女子医科大学医学部卒業。東京女子医科大学病院、河北総合病院、自治医科大学を経て、2006年からNTT東日本関東病院勤務。日本血液学会血液専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本輸血・細胞治療学会認定医。